開催レポート 8日目
3月10日(金) vol.3
映画の可能性を追求する監督の挑戦『暗くなるまでには』
《コンペティション部門》『暗くなるまでには』のアノーチャ・スウィチャーゴーンポン監督が上映後に登壇されました。

本作は撮影までに6年かかったとのこと。監督は「きっかけになったことは2つあります。1つ目は10年前に撮ったショートフィルム『Graceland』でそのキャラクターを発展させようとしたこと。もう1つは私が生まれた1976年にタイでデモに参加した人たちが大量に殺された事件です」」と述べ、「この映画は歴史を語りたいわけではない。ドキュメンタリー映画ではないのです。ですが、過去に起こった出来事に対してどうすれば事実に迫れるかを考えました。事件に対する記憶や経験もないのですが、どうすれば真実に迫れるかを考えつくりました」と熱く語られました。


観客から劇中の虫の鳴き声や鳥の声、草や木の葉が揺れる音などが強調されていたことについて、その意図を聞かれるとアノーチャ・スウィチャーゴーンポン監督は「とてもいい質問で初めていただいた質問です。ありがとうございます」とお礼を述べた上で「虫の音は実際に撮影現場で聞こえた音です。撮影の前にはロケハンをしたのですが、虫の声がすごく聞こえましたし、そのおかげで静かすぎて虫の声しかないというシーンも作りました。自然の力はコントロールできないのです。少なくとも編集している時に虫の声がセリフに被ることもありましたし、風の音、虫の声などはあえて意図的に入れたのです」と説明されました。


また、物語の中で描く人物について「この中に出てくる登場人物のことは全て現在起こっていることです。私はこれらのことに順番はつけていません。映画監督として“映画”は時間と場所と人とが遊べるものだと思っています。どういう風に彼らが繋がっているのか、などはあえて説明したくないのです。観客の方に繋がっている、繋がっていないなどを自分で考えていただきたいと思います」
あらゆる面で映画の可能性を信じるアノーチャ・スウィチャーゴーンポン監督の眼差しが印象的な時間でした。


男は顔出しNG、女は美化?!それでこそ共振できるエンターテイメントに! 『女士の仇討』
特集企画《Special Focus on Hong Kong 2017》『女士の仇討』上映後、ファイアー・リー(火火)監督がご登壇。「こんばんは!夜遅くに本作を観ていただきありがとうございます。女性のみなさんは映画を見てスカッとされましたか?男性のみなさんは、今晩は安全なので安心してもらえれば(笑)と思っています」と1人の男性を女性たちが仇討ちする物語をなぞらえ挨拶されたファイアー・リー監督。

劇中、その仇討ちされる男性本人の顔は出ないまま進行することについて監督は「この役にスターを起用するとわかりやすいが、顔を見せないことで作品を観る人が自分の彼氏や夫などに置き換えられるようにしたのです」といたずらっこのように笑みを浮かべお話しに。「一方で、映画の作品としてみせるために、女性は美化していますよ。夫に『あなた浮気しているんじゃない?』という光景はよくあることですが、街のどこにでもいるようなおばちゃんが主演では、誰も映画を見てくれないのですからね」と監督はお茶目に付け加えられました。


ブルース・リーの映画『ドラゴン危機一髪』などでも使われている“龍華酒店”がロケ場所に選ばれていることについて問われると、監督は「子供の頃、“龍華酒店”のことやブルース・リーが格好良かったという話はよく聞いていました。現在は鳩料理で有名なレストランになっていますが、今の香港人はあまり行かない場所になっています。20年後、30年後には覚えている人がいなくなると思ったので、今回、80周年を迎えた“龍華酒店”を記念に映画で残しておきたかったのです」と語られました。


さて、会場には、香港の配給会社が日本語タイトルをつけたオリジナルポスターが飾られていました。ファイアー・リー監督は「『女たちの復讐(香港の配給会社が命名)』と『女士の仇討(大阪アジアン映画祭が命名)』のどちらがいいと思いますか?今日の上映は、世界初上映なので皆さんの意見は重要なのです(笑)」と会場へ問いかける場面も。
ファイアー・リー監督の元気いっぱいなトークに、パワーをチャージされた観客は遅い時間ながらも足並み軽く笑顔で劇場を後にされていました。


タイ国王陛下からの音楽の贈り物を映像化。大阪にも届きました!『ギフト』
特集企画《ニューアクション! サウスイースト》、日タイ修好130周年 タイ映画プロモーション『ギフト』の上映が行われ、チャヤノップ・ブンプラゴーブ監督とグリアングライ・ワチラタンポーン監督が観客の温かい拍手に包まれて登壇されました。

「大阪の皆様、ありがとうございます。上映中に笑い声が聞こえてきました。私の映画が皆さんを幸せにできたのかなと思うと私も幸せな気持ちになります」とにこやかにご挨拶。本作は3話のオムニバスが1つにつながる物語。それを、4人の監督で担当されています。この作業分担についてチャヤノップ・ブンプラゴーブ監督は「私たちで最初のパートを共同監督しました。すごく闘って、その結果できたのがあの映画です」と述べ、お二人で「闘いました」としみじみ。

グリアングライ・ワチラタンポーン監督

チャヤノップ・ブンプラゴーブ監督
音楽を愛し、自ら多くの作詞・作曲を手掛けられたタイの国王陛下。その国王が作曲された楽曲というと近寄りがたい雰囲気があるものを、人々に伝わりやすいようポップにアレンジをして使用した本作では、“国王の音楽が人々に届きますように”という想いを込めてつくられているそう。「実は国王もこれらの曲を国民への贈り物(ギフト)としてつくられていたのです。3話目に使用した曲は65年前に国王陛下が作曲されたもので、“国民への新年の贈りもの”という意味が込められて作曲されたようなのです。そのことを3話目を担当したジラ・マリクン監督が、『全体コンセプトとして音楽をプレゼントする、というのは素敵じゃないか』と決め、色々な機会で音楽というものは贈り合えるのだということを体現していく内容にしました」と作品の成り立ちについて詳しく話されました。

ちなみに、このプロジェクトは2年前、国王陛下がお亡くなりになる以前から進められていたもの。悲報が入った時には撮影も編集も終わっていたので、内容の変更は一切していないものの、予告編は国王の音楽の才能にフォーカスしたものへ意識的に変更したとか。
一方、両監督の音楽経験について聞かれると「私たちは2人とも中学の時から楽器を演奏してきました。大学1年の時に知り合って一緒にバンドをするようになったのです。音楽を演奏することは、まるでお互いに呼応しあって、会話するような感じでした。音楽を映画に取り入れるということは、ぼくたちにとっては全然難しいことではなくて、2人とも音楽を理解しているし、音楽のどういうところを取り入れたいか、というのをよくわかっていましたから」と互いにお話しに。


また両監督が担当された1話目のアイディアについて「1枚の写真を見たことがきっかけとなりました。それは米国オバマ大統領の大統領就任式のリハーサルの写真があって、代役の人が『オバマ』、『ミシェル・オバマ』というネームカードをそれぞれつけて座っている写真を見た時に『これだ!』と思ったのです。一度も出会ったことのない男女が夫婦役でリハーサルをするということで一日中一緒になる理由になるし、これはラブコメに使えるアイディアだ、とひらめきました」と明かしました。
終始笑顔のチャヤノップ・ブンプラゴーブ監督とグリアングライ・ワチラタンポーン監督のお話は、観客にも素敵なギフトとなりました。




フィリピンの美しき町バレルが引き寄せ完成した『黙示録の子』
特集企画《アジアの失職、求職、労働現場》『黙示録の子』が上映され、マリオ・コルネホ監督が上映後登壇されました。
タイトルになっている『黙示録の子』とは、フランシス・フォード・コッポラ監督のベトナム戦争を描く『地獄の黙示録』の撮影がベトナムではなく、フィリピンで行われた事実から、その長期化した撮影期間中に監督の子として生まれた、とまことしやかに言われている男性のことを言い表しています。

そもそも、『地獄の黙示録』を題材にした理由についてマリオ・コルネホ監督は「映画を撮るにあたり、“大人になって歳を重ねていくこと”、“人のライフスタイルが時間と共にどう変化していくのか”を題材にしたいと思いました。そして、バレルという町で映画を撮ろうと思った時、どうしてサーフィンが盛んなのか興味を持ったのです」と話され、そこで、『地獄の黙示録』と結びついたことを明かしました。「つまり、バレルの町では『地獄の黙示録』撮影後にサーフィンが始まったと言われている、ということなのです」と監督。「しかし実際は、日本のウィンドサーファーがボードを持ってきたことが始まりらしいのですけどね」と付け加えられました。

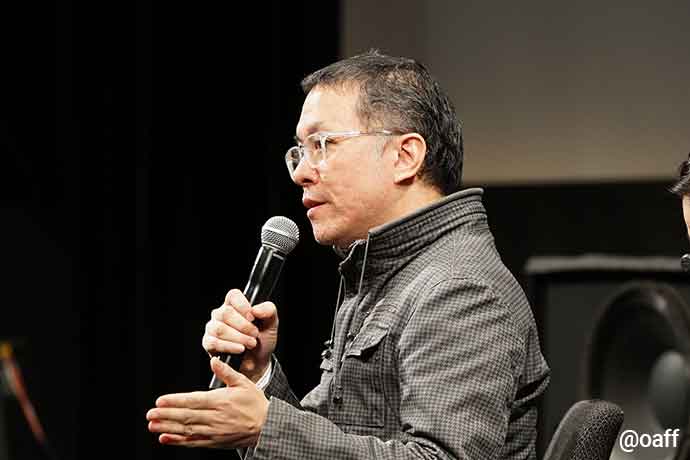
また、本作撮影にむけ「自分も父となり、自分の人生について考えた時、とてもパーソナルなものを描きたいと思いました」と述べ「劇中、父親役の俳優は出ていないが、父に関する映画だと考えています」と語られました。


あまりにも印象的なサーフィンのシーンですが、役者陣は皆、サーフィン素人だったとか。主役のシド・ルセロさんはサーフィンインストラクター役でもあるので、撮影前に特訓された、とのこと。また、複雑に展開する男女の恋話の中で、一番年下の役を演じたアニカ・ドロニウスさんについては「登場人物は皆、行き詰まり問題を抱えている。しかし、ラストで彼女が町から出ていくのは、彼女だけが行き詰まらない役割を担っており、それが重要なのです」と解説されました。
ちなみに、マリオ・コルネホ監督の奥様は本作のプロデューサーでもあることについて「喧嘩をするのは、映画のことだけですよ」とのコメントに会場も笑顔になりました。




大阪を楽しんでくださったマリオ・コルネホ監督。