シンポジウム:高層化するアジアの想像力-「生きる」と「死ぬ」のほとりで

大阪歴史博物館にて「高層化するアジアの想像力-「生きる」と「死ぬ」のほとりで」をテーマにしたシンポジウムが開かれ、マレーシア映画文化研究会の山本博之氏が司会をつとめるなか、『KIL』のニック アミール・ムスタファ監督、『ほとりの朔子』の深田晃司監督がパネリストとして登壇しました。
映画の製作秘話、日本・マレーシアの映画製作状況、『KIL』のプロデューサーを務めたレワン・イスファク氏が監督した短編映画の上映もあり、マレーシア映画の現状を説明していただきました。
 ニック アミール・ムスタファ監督
ニック アミール・ムスタファ監督 深田晃司監督
深田晃司監督 山本博之氏
山本博之氏

ニック アミール・ムスタファ監督
イスラム社会であるマレーシアにおいて、自殺は重い罪でありタブーだという考えはあります。上映当初は自殺というテーマについて問題になったのは事実ですが、この映画は自殺というネガティブなテーマを通じて、ポジティブに生きるという映画なので、公開されると意外に反応もよく、特に若い世代から支持してもらえました。また観る人にとってもいろんな見方をしてもらえているのも面白いです。
マレーシアの映画産業では商業かアートかに分かれてしまうのですが、その中間を目指して今回は製作しました。今後も尊敬している監督の一人である故ヤスミン・アフマド監督のように民族に関係なくマレーシア人全員、そして海外の人にも楽しんでもらえる映画をつくっていきたいと思っています。
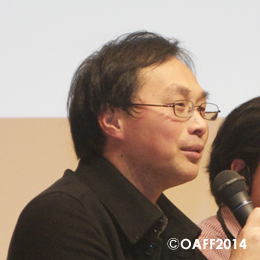
深田晃司監督
『KIL』を鑑賞して、クリアな演出、綺麗な映像、不透明な現代社会を描いていておもしろかった。自殺したい主人公というテーマについても、生きるか死ぬかという判断がかつては社会的立場で決められていたのに対し、現代は個人の判断に委ねられているが、死ぬ選択肢があるということがひっくりかえって逆に生きることに前向きな変化を与えてくれていることもあるのではないか。特に冒頭と最後のシーンで同じ風景が使われていたが、主人公の気持ちの変化を観客が感じることが出来るようになっているのが印象的でした。
またこの自殺支援している会社が劇中に出てきますが、この会社のモデルがスイスに実在するのは驚きです。是非とも取材に行ってみたい。

ボガーツカフェにてトークイベント「台湾の今昔を語る」が開催され、30年近く映画製作に携る『戦酒』のピーター・タン監督、1960年代頃の台湾語映画の製作現場を舞台とした『おばあちゃんの夢中恋人』の北村豊晴監督、シャオ・リーショウ監督をゲストに迎え始まりました。
タン監督は、実体験から台湾映画の昔を紹介。また、現状について「映画撮影は宝くじ。賞を取れば注目されるが、埋もれてしまう良い作品も沢山ある。それでも台湾映画には未来がある。政府も支援していくべきだ」と語り、熱い思いが伝わってきました。
マイクが北村監督にわたると、真剣に聞き入っていた会場は笑いの渦に。シャオ監督も「十数年前の北村監督はキムタク似だったのに」とコメントし、またも会場は大爆笑の一幕も。各作品のアイデアの素や秘話も次々と明かされ、Q&Aの時間へ。
台詞が標準的な中国語から台湾なまりの中国語へ変化していることが話題にあがり、「それはアフレコから同時録音への技術進歩や自然さを追求した結果」とタン監督。また、シャオ監督が、「現在は北部より台湾語がより話されている南部の方が興行成績も良いので、台湾語の出現率が増加している」とも話されました。
 ピーター・タン監督
ピーター・タン監督 北村豊晴監督
北村豊晴監督 シャオ・リーショウ監督
シャオ・リーショウ監督
「日本で撮影するならどんな映画を撮りたいですか」という質問に、タン監督は、日本で財を成した金門島出身者を題材にした企画があることを明かされました。また、北村監督は、「出身地の滋賀を舞台に、作品をつくりたい」とし、シャオ監督は「日本の漫画を実写化してみたい」とそれぞれ語られました。
シンポジウム終了後も、サインに握手に写真にと、監督たちを取り囲んで会場は大盛り上がりでした。










