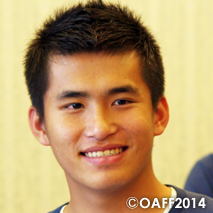台湾で現在大ヒットを記録している『KANO』。台湾が日本統治下にあった1920年代。全国中等学校優勝野球大会(現・全国高等学校野球選手権大会)の台湾代表として勝ち上がり、準優勝を記録した嘉義農林高校野球部(通称カノウ=KANO、以後嘉農)の史実に基づき、当時の台湾社会、そして野球を通して台湾人・原住民・日本人が心を通わせていく様を感動的に綴った超大作。


その製作総指揮ウェイ・ダーションさん、監督マー・ジーシアンさん、永瀬正敏さん、坂井真紀さんに、この作品の裏話をうかがいました。
――台湾の日本植民地時代というデリケートな時代背景を映画化するにあたって気をつけたこと。日本語のセリフが大半を占める作品を作る苦労は?

ウェイ・ダーションさん(以下、ウェイ):前作の『セデック・バレ』![]() の時から台湾の日本植民地時代をリサーチしていたので、あの時代のことはよく理解していました。『セデック・バレ』
の時から台湾の日本植民地時代をリサーチしていたので、あの時代のことはよく理解していました。『セデック・バレ』![]() で描いたのは、民族間の衝突・対立でしたが、『KANO』は民族間のギャップを越えた団結がテーマですので、そういった時代背景を念頭に置きながらも、極力物語の中では遠ざけ、登場するキャラクターの物語にスポットが当たるようにしました。また、日本語のセリフに関しても、日本の俳優さん、スタッフの皆さんの優秀さによって助けられました。たしかに言葉が通じないことで最初は通訳さんを介したやりとりで戸惑いがありましたが、撮影が進むにつれて通訳さんを介す前にお互いにわかりあえるようになっていきました。映画という共通言語を持った私たちの現場では、言葉を越えていけることを確信できた仕事となりました。
で描いたのは、民族間の衝突・対立でしたが、『KANO』は民族間のギャップを越えた団結がテーマですので、そういった時代背景を念頭に置きながらも、極力物語の中では遠ざけ、登場するキャラクターの物語にスポットが当たるようにしました。また、日本語のセリフに関しても、日本の俳優さん、スタッフの皆さんの優秀さによって助けられました。たしかに言葉が通じないことで最初は通訳さんを介したやりとりで戸惑いがありましたが、撮影が進むにつれて通訳さんを介す前にお互いにわかりあえるようになっていきました。映画という共通言語を持った私たちの現場では、言葉を越えていけることを確信できた仕事となりました。
マー・ジーシアンさん(以下、マー):歴史事実に関しては徹底的な時代考証を行い、あの時代の台湾の雰囲気を再現しました。時代背景は複雑ではありますが、私たちが注力したのはその時代の持っている空気感や雰囲気。あの時代に生きた人たちが、どうやって暮らしていたかを描くことに集中しました。

永瀬正敏さん(以下、永瀬):もちろん僕たちも演じるためにはリサーチを重ねました。僕に関して言えば、近藤先生に教わった生徒の皆さんが、どういう経験をされ、どういう事実があったのかを知り、それが非常に素晴らしいエピソードだったことが印象的でした。演者としてこの素晴らしい事実を、映画を通して広く知ってもらうことができれば、と思い、撮影に挑みました。言葉の壁を感じることもなかったですね。ウェイさんもおっしゃったとおり、映画という共通言語を持つことで、多少の苦労は乗り越えられることを知りましたよ。そして言語のギャップよりもなによりも驚かされたのは、製作の規模です。ある日は街ができていて、ある日は船ができていて、またある日は甲子園球場ができている、というオープンセット。これを見た時に、とんでもない作品に関わっていると実感しました(笑)。

坂井真紀さん(以下、坂井):私も永瀬さんと同じくリサーチをして、当時の人たちが一つの目標に向かって一致団結して乗り越えていこうとする姿に感銘を受けました。登場するキャラクター一人一人が素敵で、この作品に参加できたことをうれしく思っています。それと、非常にこの現場は厳しかったんですね。特に高校球児を演じた皆さんは本当によく働いていたのが印象的でした。撮影の合間も、終わった後も、休むことなく野球の練習、セリフの練習に励んでいるんですよ。あぁ、まったく休ませないのね、って思ったくらい。それを見ていたので、自分としても「私もがんばらなくちゃ」と奮起させられたものです。
――作品作りで大切にしていたことなど。

マー:小学校の頃から僕は野球をしていたので、甲子園というところが日本の高校球児にとっての聖地だということは知っていました。じつは2012年に甲子園の高校野球を観戦したことがあります。そのときに、選手達もですが、観客はどうやって応援しているのか、記者達はどうやってみているのか、というところをロケハンしていました。あの経験があったから、甲子園のシーンが描けたんですね。セットは作ることはできますが、中にいる人たちは生身の人間ですから。
ウェイ:日本の高校野球、甲子園には毎年毎年ドラマがあります。必ず毎年違った感動と興奮があるこの甲子園というものが、高校球児達にとってどういうものなのか。そして、毎年行われてはいるものの、彼らにとっては一度しかないチャンスである甲子園とは? そこを描きたかったんですね。台湾では、このメッセージを受け止めてくれた方が多いのか、普段野球に無関心だった女性がこの映画をきっかけに野球に興味を持ち始めているというケースもあります。坂井さんはどう思います?(笑)
坂井:じつは私自身はもともと野球が好きで、小さいころは少女野球のチームに入りたかったくらいなんですよ(笑)。
ウェイ:え、少女野球が日本にはあるんですか! 台湾だと男女混合チームなんですよ(笑)。

坂井:ええ、そうなんです。だから野球に夢中になるということも理解できるんですよ。だけど、甲子園の歴史というのがこんなにも長いものだったことを知ったのは、この映画がきっかけです。本当に驚かされましたし、長く続いていて、しかも毎年夢中になって見てしまう理由というのも、この映画を通して再確認できた気がします。
永瀬:なによりこの映画は、当時に忠実に、その時代を生きた人をそのままに描いてくれたことに感謝しています。よく海外で日本を描こうとすると、チョンマゲで英語ペラペラのキャストが出てくるようなチグハグなことが起きてしまうんですが、この映画ではまったくそのような不安がありません。演技経験のない台湾の若者達に、敢えて日本語のセリフにも挑戦してもらい、日本映画でもなかなかできないほど驚くべき当時の再現をしてくださいました。これにはとにかく大感謝をしています。
引き続き、本作で嘉農野球部の新任監督・近藤兵太郎を演じた永瀬正敏さん、そして嘉農野球部のメンバーを演じた11人を迎えお話しをうかがいました。

――この作品で描かれていた嘉農の事実は、キャスティング前にご存じでしたか?
永瀬:いえ、まったく知らない話でした。この作品のお話をいただいたことで、いろいろとリサーチをしたんですが、こんな素晴らしい話があったことを映画で広めることができるなら、と思い、出演することを決めました。今日は11人の生徒たちが集まりましたが、彼らもまったく知らない話だったようです。(11人ともうなづく)
――野球に関しては皆さんは経験者ということですが、演技は初めてだったんですよね。
ツァオ・ヨウニン(曹佑寧)さん(以下、ツァオ):演技をすること自体初めてでしたし、日本語もまったく初めてで。
――この中で、日本語、もしくは日本文化についてなじみがあった方はいらっしゃいますか?
(台湾からの8人は一様に首を横にふる)

永瀬:だからこの映画は本当にすごい挑戦だったんですよ。彼らは野球に関しては一流の技術を持っていたけど、演技はもちろん、日本に関する知識や日本語を学んだこともなかったんですから。彼らのがんばりには、僕はまったくかないません。僕は彼らのコーチの役を演じましたが、実際には彼らは同じ現場で奮闘した仲間だと思っています。
ツァオ:野球のことは安心できるんですけど、それ以外のことは全部が挑戦でした。だけど、永瀬さんはもちろんですが、日本人のキャストの大倉さん、山室さん、飯田さんには現場で日本語を教わることができたので助かりましたね。

山室光太朗さん(以下、山室/写真右上):とはいっても、僕たちも普段使わないような日本語のセリフばかりだったので苦労したんです。ちょっと気を緩めると普段使っている現代的な日本語が出てしまうので。それはアノ時代では不自然ですからね。
大倉裕真さん(以下、大倉/写真右下):それに僕たちも彼らには助けられることがたくさんありました。僕はファーストだったので、両脚を開く動作が必要だったんですが、とにかく体が硬くて。5~6人がかりで柔軟体操をしたりで。それで「ピートエ」って言葉を教えられたんですけど……(台湾キャスト全員爆笑。ピートエは「二股」の意味)。
飯田のえるさん(以下、飯田):僕たちは永瀬さんよりもちょっと早めに現場入りしていたので、全キャストがそろう前にみんなと打ち解けていましたね(笑)。
永瀬:2週間くらい先だったのかな。場をあっためておいてくれたんですよ(笑)。
――とはいえ、現場は過酷だったんですよね。
永瀬:夏のようなシーンが多いんですが、とにかく寒くて……(笑)。じつはあの撮影は乾期に入った時期だったんですが、想像していたよりも寒い。どしゃ降りの雨のシーンがあるんですが、あれは特に寒くて、みんなずぶ濡れになって風にさらされまして。

ツァオ(写真左):あれは本当に辛かったです。濡れたら乾いたものに着替えて別のシーンの撮影をするんですが、また濡れた衣装に着替え直すこともあって。それで演技もしないといけないですから。
永瀬:順撮りじゃなかったんですよね。だから、彼らはわざわざ濡れた衣装に着替え直すことが何度もあったんです。映画の経験のない人たちがそんなことまでしているのに、さらに演技を求められるなんて過酷だったと思いますよ。僕も田んぼに突っ伏してずぶ濡れになるシーンもありましたけど(笑)。
――近藤先生の厳しい指導をリサーチされたとか。
永瀬:近藤先生の教え子さんにお話をうかがいましたが、とても厳格な指導をされたと聞きました。
ツァオ:甲子園に出場するということはそれくらい厳しいことを経ないといけないことなんでしょう。日本の高校球児のがんばりは、僕ら野球をやっている者としては勉強になります。
永瀬:とはいえ、僕がもしここにいる彼らの年代で、この映画にキャスティングされていたとしたら逃げ出してますよ。俳優をやっていたとしても、彼らの役は僕にはとてもじゃないけど務まらない。なにせ、全然経験したことがない言語のセリフを、一からたたきこんで、その上で演技したんですから!

――日本語のセリフはどうやって覚えたんですか?
ツァオ、チャン・ホンイー(張弘邑)さん:わからないところを、日本人キャストに聞いたり……。
山室:僕たちもセリフを覚えないといけないので、一緒にがんばりました(笑)。
飯田(写真右):でも、当時の日本語のセリフは頭に入っても、つい自分たちが今使っている日本語の感じになってしまうんですよね(笑)。
大倉:「超」とかついつい出てしまったりして。
永瀬:おいおい、それはないよ、ってことが何度かありましたよね。ただデリケートな時代背景だったんで、和製英語が使われていたかもしれないこともあるんですよ。たとえば「ラッキー」とか。戦争が始まってからはすべて日本語になったと思うんですが、「ショート」とか「イニング」とか「スライダー」とかは普通に使われていた時代ですから。その点でも非常にデリケートで難しい時代背景の映画だったと思います。
――では、最後に。台湾以外で初めての『KANO』上映が行われますが、日本の皆さんにはどう観てもらいたいかを一人ずつ。
(写真左より)
シエ・ジュンチョン(謝竣晟)さん:日本の皆さんも、あらゆるシーンで共感をしてもらえると思うので、多くの人に観てもらいたいです。
チェン・ジンホン(陳勁宏)さん:スポーツマンシップをきちんと描いた映画だと思います。そういったところを観てもらえるといいですね。
ウェイ・チーアン(魏祈安)さん:野球の技術的なところはもちろんなんですが、エモーショナルなシーンが多いので必ず感動してもらえると思います。
シエ・ジュンジエ(謝竣倢)さん:さっきも話に出ましたが、雨のシーンは僕らも本当にがんばりました。是非そこを観てもらいたいです。
チェン・ビンホン(鄭秉宏)さん:何度見直しても、僕ら自身誇らしい作品になっていると思います。スタッフも出演者も皆さん素晴らしい働きをした作品ですので、そこを感じてもらえるとうれしいです。
大倉:嘉農のチームが甲子園で見せたものと同じく、この映画はみんなの努力と涙の結晶だと思います。
飯田:半年間、撮影にかかっていたんですが、僕らが一丸となってがんばった6カ月間を観て欲しいです。日本語のセリフでみんなががんばったところも感じてもらえるといいですね。
山室:登場キャラクターの一人一人のエピソードが濃く、それぞれの人生が詰まった映画です。なので、観る人は必ずどこかに共感をしてもらえると思います。
ツァイ・ユーファン(蔡佑梵)さん:この映画で描かれているスピリットは、野球だけじゃなくどんな人にも応用できると思うんです。かならず皆さんとこの思いを共有できると思います。
チャン・ホンイー(張弘邑)さん:台湾ではすでに多くの人々に支えられている映画です。きっと日本人にも同じように受け入れてもらえる映画だと思います。
ツァオ:チームが一致団結する素晴らしさ、そして何ごともあきらめずに立ち向かうこと。スポーツ選手の抱える裏のがんばりを観ていただけるとうれしいです。
永瀬:近藤先生の時代の話ではありますが、この映画で描かれていることは普遍的なことです。今の我々にも必ず響く映画だと思っています。正直言って、最初は「3時間5分」という上映時間を聞いて、主演の僕ですら不安に感じました。ですが、ひとたび観てしまうとまったくその長さを感じません。その驚きはこれから観る皆さんも体験していただけると思います。この作品が、台湾、日本のみならず、広く世界に羽ばたいていけるだけのメッセージを携えたものだということを信じていますので、日本の皆さんにも応援してもらえるとうれしいです。